○御所車型(2輪 主柱4本 森・袋井形)


・森町 本町 水哉社 ・袋井 西通り、三門町 月桂社
まことに申し訳ない話なのですが、私が見る限り森・袋井の型式に差異は全くと言って良いほど感じません。
漆の有り無しはあくまで「装飾」の問題であり、それは「用途」の違いではないからです。彫物、組物などと同じ
考えで構わないと思うのです。それぞれの地区による「色」の様なものと捉えても差し支えないのではないでしょうか。
現実に「森は漆」、と言われていますが、天宮地区はその用いた木材が天宮神社のものであることから
そのままの白木でやっていくのが良い、という考え方ですし、「漆がない」と言われていた袋井でも最近は漆が
入っている地域が多くなりました。互いのエリアでは異色の存在かもしれませんがだからと言って「型式が違う」
などということは決してありえない話です。
ですからここでは一つの形式として考えています。森にも袋井にも歴史はありますし、それぞれの良いところが
ありますので、双方に敬意を表して「森・袋井」と表記します。(袋井・森でも構わないでしょうが、語呂的に)
基本構造は直径5~6尺(約1,500~1,800mm)の2輪の上に枠木があり、そこから4本柱によって屋根
(陸屋根)が設けられている。(構造上、柱が追加されていることもある)前方には御簾と脇障子あるいは
袖障子と呼ばれる耳状の彫刻の入った羽根板がある。
左右側面は障子で後方は開放されている。御簾の前と陸屋根には高覧があることから「高欄型」とも
呼ばれるが、高欄そのものは他の型式にも存在するので、形状が似ている「御所車型」とこのサイトでは
表記している。
手木の幅は4尺から6尺。地区の人数や道路の状況により変えているものと考えられるが、現在では
5~6尺が主流で、組物や支輪周りの彫物なども含めて複雑化・大規模化する傾向がある。
引廻しは手木、枠木を胸から脇の下で抑えて巡航する。
詳しくは
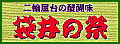
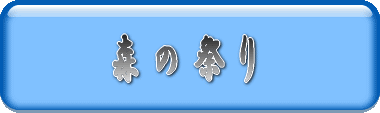 両サイトさんを御参照下さい。
両サイトさんを御参照下さい。○御所車型(2輪 主柱4本 掛川形 側面障子:前高欄)


・菊川市 三丁目 ・菊川市 ニ丁目
こちらもまことに申し訳ない話なのですが、祭典日が私の地区とずれることが無いために市街地の屋台を拝見した
ことがありません。また皆様に御教授頂ければ幸いです。
掛川形に関しては市街地において旧来の屋台が複数存在しています。当時の面影を大事に保存していらっしゃる
ので、型式推移の検証は進めていこうと思っています。
とにかく掛川形は亜種が多いので分類がとても困難です。
詳しくは
 さんのサイトを御参照下さい。
さんのサイトを御参照下さい。基本構造は森・袋井型と酷似するが、小太鼓を叩く出高欄が存在する。また陸屋根下部の欄間には彫物もしくは
蒔絵が入り、組物は無いか至ってシンプルなものを取り入れている。しかし近年は森・袋井形にある出先組物が
取り込まれた地区もある。また側面障子前方が開放されて高欄が設けられ、横から見ると段差があるように見える
タイプもある。また正面御簾脇の脇障子と呼ばれる耳状の羽根板は基本的に無いが、これまた森・袋井形からの
影響か最近取り込まれた地区もある。
○御所車型(2輪 主柱4本 掛川形 側面障子:側面全面)


・掛川市 幡鎌 猿田彦社 ・菊川市 上倉沢 駒形社
基本構造は掛川形。障子が側面全面に存在する。おそらく森・袋井形の影響を受けていると思われ、脇障子も
ある地区と無い地区が混在する。
掛川市内にはおそらく2輪御所車型の中でも最古に近い屋台があります。喜町さんと中町さんの屋台がそれですが
あいにく手持ちの写真がありませんので記述だけにします。
喜町さんは江戸後期に京都で購入と言われており、この屋台がもしかすると今ある御所車型の原点になった
可能性もあります。
中町さんは2層の屋台で現在は異色の存在ですが、まだ電線が引かれていなかった時代には2層・3層の屋台は
あちらこちらで見られました。
いずれにしても掛川形、というよりは原・御所車形とでも言うべき存在かもしれませんが、もう少し調査させて下さい。
○御所車型(2輪 主柱4本 日坂形)


・掛川市 日坂 下町 常磐閣 ・島田市 菊川 菊川連
基本構造は森・袋井形や掛川形に準ずるが、大きく異なる点は組物が無く、屋根上に朝顔と呼ばれる
格子模様の飾りがあること。その朝顔の中には高覧があり、御所車型の原点ではないかとも言われる
シンプルな様相を呈する。ずり棒がないのが基本でダイナミックな引廻しができる。支輪に蒔絵が多い
のも特徴。正面横に展開する脇障子、正面の前高欄は無い。
○御所車型(2輪 主柱4本 唐破風屋根形)


・浜松市天竜区春野町 犬居 龍勢社 ・菊川市 潮海寺
浜松市天竜区春野町と菊川市潮海寺で見られる型式。犬居には複数台あり、4輪唐破風屋根屋台の改造と
言われている。枠木から下は通常の御所車型を踏襲する。
一方潮海寺は石階段を昇降する屋台として有名であり、そのため車の径が小さい。何ゆえ唐破風屋根
なのかは調査不足で不明だが、潮海寺囃子もあることから独自の文化が持ち込まれた可能性が高い。
○御所車型(2輪 主柱4本 中泉形 春野式)


・浜松市天竜区春野町 宮川(高瀬) 高栄社 ・浜松市天竜区春野町 領家(原) 北嶺社
(骨折野郎さん撮影)
浜松市天竜区春野町にて散見される形。後述の中泉形に酷似するが後方に袖障子を有する。
中泉形と異なり主柱は4本であることから改造から生まれた形ではない。後方に袖障子というのは
4輪屋台の掛塚型に準ずるものであり、掛塚からの4輪文化、森町からの2輪文化の融合として
上記の唐破風屋根型と双璧を成している。
○御所車型(2輪 主柱5本 中泉形)



・磐田市 中泉 七軒町 騰龍社 ・磐田市 中泉 東町 東組 ・菊川市 段横地 段組
その昔、一本柱万度型を改造してできたと言われる形。中泉から派生したためこう呼ばれている。
遠目に通常の御所車型に見えるが、脇障子、側面障子や御簾はなく全周にわたり高覧がある。
2輪の径は小さく一本柱万度型とほぼ同様の1,400mm前後。よって引廻しは腰のあたりで手木や
枠木を抑えて巡航する。屋台中央部に5本目の柱が立っていて、そこを梯子として高覧へと昇降する
場合もある。後方の腰板には引き出しが格納されていて小物類を格納できる。
現在は中泉から分散する傾向にあり、磐田市豊田町池田や菊川地内に点在する。
詳しくは
 さんのサイトを御参照下さい。
さんのサイトを御参照下さい。平成23年9月17日 改訂 (菊川形→掛川形・脇障子前高欄)
平成23年9月21日 改訂 (脇障子→側面障子 に伴う微校正)
平成24年6月15日 改訂 (中泉型春野式追加)